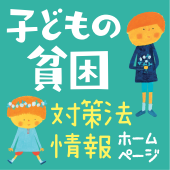6月17日(日)2012年総会開催のお知らせ
月曜日, 5月 21st, 20126月17日にネットワークの総会を行います。
参加は自由ですので、みなさまのお越しをお待ちしております。
【日時・場所】
2012/6/17(日)18:20~20:00
立教大学池袋キャンパス12号館地下第3・4会議室にて
池袋キャンパスマップ
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/
次回ネットワーク会議は5/10(木)に開催いたします
火曜日, 4月 10th, 20123/22(木)に立教大学にて開催致しました
ネットワーク会議には33名もの方にご参加頂きました。
お忙しい中お集まり頂きありがとうございました。
次回ネットワーク会議は
5/10(木)に開催いたします。
時間:5/10(木)19:00~21:00
場所:立教大学 池袋キャンパス
12号館第3・第4会議室
池袋キャンパスマップ
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/
<主な議題>
1.ミニレクチャー「ひの・子ども支援塾の活動について」
HINO飛ぶ教室 滝口仁さんよりお話を伺います。
2.若者(高校生・大学生)からの発信×交流
若者世代のみなさんの声を聴きながら交流の時間を
もちます。
3.グループトークでの交流
2012年度にネットワークでやってみたいこと、子どもの貧困
についての思いなど、交流しましょう。
4.みなさんとの情報交換
・2012年度ネットワークの活動について
・6月の総会について
・イベント告知 など
以上よろしくお願いいたします。
共同代表:湯澤直美、平湯真人、三輪ほう子
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
2012年3月『大震災と子どもの貧困白書』刊行のお知らせ
水曜日, 3月 7th, 2012昨夏以来準備してまいりました
『大震災と子どもの貧困白書』が、刊行されました。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワークが編者となって刊行する
2冊めの本です。(1冊めは、『イギリスに学ぶ子どもの貧困解決』)
「つなみはどろぼうだ
私のたからものを ぜんぶもっていったよ
おじいちゃんに 家に 私のちょきん通帳」
これは、巻頭写真メッセージにある岩手の子どものことばです。
本書のおとなの執筆者総数は60人。
この本に書いてくれた、あるいは作文や絵・写真で登場してくれた
子どもたち・若者たち(大学生以下)は、合計69人となります。
予想以上に、子どもたち・若者たちの姿と声がつまった本に仕上がりました。
また、本書の編集委員やご執筆者・ご協力者のなかには、
このメーリングリストが出会いのきっかけとなった方が何人もいらっしゃいます。
大きな意味で、私たちのネットワークのつながりのなかから生まれた本と
いえます。お力添えいただいたみなさまに、心より感謝申し上げます。
チラシは、こちらをご参照ください。
『大震災と子どもの貧困白書』両面チラシ
『大震災と子どもの貧困白書』チラシ表面:白黒印刷用
『大震災と子どもの貧困白書』表紙
以下、出版のご案内をいたします。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク
共同代表:湯澤直美、平湯真人、三輪ほう子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『大震災と子どもの貧困白書』
編集委員代表
湯澤直美/立教大学コミュニティ福祉学部教授・
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表
編集委員
小野寺けい子/盛岡医療生活協同組合理事長・川久保病院小児科医師
こどもの“ふつう”を考える福祉・教育・医療の会
賀屋義郎/民主教育をすすめる宮城の会事務局長・
東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター事務局次長
丹波史紀/福島大学行政政策学類准教授・福島大学災害復興研究所
反貧困ネットワークふくしま共同代表
田中孝彦/武庫川女子大学教育研究所教授・日本臨床教育学会震災調査準備チーム
阿部 彩/国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部長
B5判 364ページ 定価3150円
発行:かもがわ出版
★ご購入は以下よりお願いいたします。
最寄りの書店さん、インターネット書店、
かもがわ出版ホームページ(送料無料)
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ta/0521.html
★集会・イベント等での販売をご希望の方は、
かもがわ出版:三輪宛、お問い合わせください。
miwa@kamogawa.co.jp
080-4456-9529
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
次回ネットワーク会議は3/22(木)に開催いたします
火曜日, 3月 6th, 20122/23(木)に立教大学にて開催致しました
ネットワーク会議には29名もの方にご参加頂きました。
お忙しい中お集まり頂きありがとうございました。
次回ネットワーク会議は
3/22(木)に開催いたします。
日時:2012/3/22(木) 19:00~21:00
場所:未定
場所と議題につきましては、
決まりしだい改めてご連絡させていただきます。
以上よろしくお願いいたします。
共同代表:湯澤直美、平湯真人、三輪ほう子
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
次回ネットワーク会議は2/23(木)に開催いたします
木曜日, 2月 2nd, 20121/19(木)に立教大学にて開催致しました
ネットワーク会議には24名もの方にご参加頂きました。
お忙しい中お集まり頂きありがとうございました。
次回ネットワーク会議は
2/23(木)に開催いたします。
日時:2012/2/23(木) 19:00~21:00
場所:未定
場所と議題につきましては、
決まりしだい改めてご連絡させていただきます。
以上よろしくお願いいたします。
共同代表:湯澤直美、平湯真人、三輪ほう子
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
2012/1/9(月・祝)公開セミナー「子どもの貧困に対する政策を考える」に共同代表湯澤が登壇いたします
火曜日, 12月 27th, 20112012/1/9(月・祝)に同志社大学にて開催される公開セミナーに
ネットワーク共同代表の湯澤直美が登壇致します。
皆さまふるってご参加下さい。
以下、公開セミナーのお知らせとなります。
———————————————————————————————
国立社会保障・人口問題研究所主催
公開セミナー「子どもの貧困に対する政策を考える」開催のご案内
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
日本の子どもの貧困率は今や15.7%である(2009年値)
ようやく「子どもの貧困」が認識されつつある日本社会だが、
子どもに対する政策は、依然として迷走状態にある。
当セミナーに日英の第一線で活躍する研究者が一堂に会する。
1999年に「子どもの貧困撲滅」を公約に掲げ、2010年には
「子どもの貧困法」を成立させたイギリスの十数年の成功と
失敗から日本が学ぶべきことは何か、子どもの貧困に対して
どのような教育、福祉、社会保障政策を打ち出していくべきか、
たっぷりと議論していく。
【開催要綱】
日 時■ 2012年1月9日(月・祝)10:00-17:00
会 場■ 同志社大学今出川校地 寒梅館ハーディーホール
(京都市上京区烏丸通今出川上る)
http://www.doshisha.ac.jp/information/facility/kanbai/
内 容■
○第Ⅰ部 日英における子ども手当・子ども給付の迷走
ジョナサン・ブラッドショー(ヨーク大学)
所 道彦(大阪市立大学)
○第Ⅱ部 子どもの貧困と社会的排除を理解する
エスター・ダーモット(ブリストル大学)
松本 伊智朗(北海道大学)
○第Ⅲ部 子どもの貧困に抗う実践プログラム
湯澤 直美(立教大学)
埋橋 孝文(同志社大学)
<挨拶・司会・コメント>
橘木 俊詔(同志社大学)
山森 亮(同志社大学)
矢野 裕俊(武庫川女子大学)
マーサ・メンセンディーク(同志社大学)
デイヴィッド・ゴードン(ブリストル大学)
◆企画◆
阿部 彩(国立社会保障・人口問題研究所)
[敬称略・順不同]
◇◇◇日英同時通訳が入ります(無料)
◇◇◇お申し込み
事前申込は不要です(入場無料)
定員800名(先着順)
◇◇◇お問合せ先
同志社大学ライフリスク研究センター事務局
tel:075-251-3728 fax:075-251-3727
email: rc-risk@mail.doshisha.ac.jp
http://liferisk.doshisha.ac.jp
自治体の就学援助制度調査にご協力下さい
月曜日, 12月 26th, 2011「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク調査チームでは、
各自治体で行われている就学援助の実態を明らかにするための調査を実施致します。
この調査には、是非多くの方に参加していただき、
お住まいの自治体の実情を調べていただきたいと考えています。
皆様のご参加により、各自治体の実際の運用を明らかにするとともに
その改善のための働きかけに結び付けることができるとよいと考えます。
調査結果は当ネットワークのホームページに公表し、
経済的な困難を抱える家庭と子どもにとって、
就学援助がより利用しやすくなるように提言をしていきたいと考えます。
学校教育にお金がかからない社会つくりを目指して、
その一歩となる調査としたいと思いますので是非とも皆様のご協力をお願いいたします。
記
○調査期間:第1次の調査期間を2012年1月20日(金)までとします。
○調査への応募の仕方
(1) 調査にご協力いただける場合には、まず、以下のアドレスにご連絡をお願い
します。
メールアドレス:syugakuenjyoアットマークgmail.com
※アットマークを@に置き換えて下さい。
件名に「就学援助制度調査への参加について」と明記してください
本文に「お名前」「お立場」「連絡が可能な電話番号」
「調査が可能な自治体名」を書き、送信してください。
(2) 本調査実施責任者が、調査対象の自治体につき、すでに調査が済んでいるか
いないかについて確認し、
その結果を返信メールでお知らせ致します。
合わせて調査マニュアル等を送信します。
(3) 調査未実施自治体であった場合に、実際の調査に進んでください。
同じ自治体に重複して調査をすることを避けるため、
必ず上記Gメールアドレス宛に、調査への参加希望のメールをいただくようにお願い
いたします。
みなさまのご協力を重ねてお願いいたします。
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク調査チーム担当
川松 亮、湯澤 直美、山野 良一
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
11月23日(水・祝)国際講演会「フィンランドの家族と福祉」を開催致します
土曜日, 10月 29th, 2011■国際講演会「フィンランドの家族と福祉
~“子どもの貧困”克服への手がかり」
日時:2011年11月23日(水曜日・祝日)13:00~16:00(12:30開場)
場所:お茶の水女子大学 共通講義棟2号館201教室
--------------------------------
ライフスタイルの変化に注目して、今日のフィンランドの子ども家族の実像と
政策の展開を示し、これからの日本の子ども・家族政策のありかたを考えます。
この講演会の目的は、単なるフィンランド礼賛ではありません。
今日のフィンランドは、離婚が頻発する社会であり、家族の姿は多様化し、
もうムーミン谷には戻れないのです。
格差や排除といった社会問題が暮らしに影を落とすリスクから
誰も逃れることはできません。しかし、子どもたちの健やかな成長よりも
大切なものが他にどれほどあるでしょうか。
フィンランドでの家族や子育てについての問題意識を分かち合いつつ、
日本の子どもの貧困問題の解決の方向性を考える手がかりを、
ご一緒に考えたいと思います。どうぞふるってご参加ください。
・講師:キンモ・ヨキネン(ユヴァスキュラ大学教授・ 家族研究センター所長)
・コメンテーター:髙橋睦子(吉備国際大学 教授)
・入場料無料・同時通訳付き
・主催:吉備国際大学大学院社会福祉学研究科
共催:「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
後援:フィンランドセンター 助成:日本学術振興会
----------------------
■参加申し込み:同時通訳の準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
参加票は発行しませんので、当日直接会場にお越しください。
(当日参加も可能です)
○参加申し込み・取材申し込みは、こちらへ>>
https://pro.form-mailer.jp/fms/93424e3723323
ファックスでの申し込みの場合:048-471-7305
「11・23講演会申し込み」と明記のうえ、
お名前、ご所属・お立場をお送りください。
※チラシのダウンロードはこちらから
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2011/11/1123finland.pdf
■会場へのアクセス
東京都文京区大塚 2-1-1 お茶の水女子大学 共通講義棟2号館
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分
都営バス「大塚二丁目」停留所下車徒歩1分
http://www.ocha.ac.jp/access/index.html
キャンパスマップ:⑥が共通講義棟2号館
http://www.ocha.ac.jp/access/campusmap_l.html
★ご注意:祝日は南門が閉まっていますので、正門からお入りください。
正門から会場まで、さらに約5分かかります。
■お問い合わせは、下記までお願いいたします。
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494【当日連絡先】
E-mail mail@end-childpoverty.jp
——————————————-
10月29日(土)学びサポート全国実践交流会を開催致します
土曜日, 10月 8th, 2011■10月29日(土)「学びサポート全国実践交流会」
チラシはこちらからダウンロード頂けます(PDF形式:1.9MB)
学びの秋です。
全国に広がっている「学びサポート」「無料塾」の実践を交流し合いませんか?
ひとり親家庭支援に力を入れた塾、家庭の温かさを生かした夕ごはん付き勉強会、
生活保護世帯の子どもたちの中3勉強会、高卒認定試験学習会…
驚くほどいろいろな学びの場が、まちの中に生まれています。
・学びサポートってなんだろう?
・私たちの地域でも始めたいのだけれど…
・被災地での学習支援をしています
・学生ボランティア、これからどうする?
あなたの実践、子どもたち・若者たちの声、喜びと悩みをいっしょにもって、お集ま
りください。
勉強に、学校に、入試に、学歴に困っている子どもたち・若者たちの助っ人、伴走者、
喜び分かち合い人、大集合!
【学びサポートとは】
経済的に困難な家庭の子どもたちに、無料または低額で、学校教育外で取り組まれる
非営利の学習支援のことです。
--------------------------------------
【開催概要】
日時:10月29日(土)10:00~16:45 ※9:30開場
場所:お茶の水女子大学/〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
共通講義棟1号館、2号館
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分
都営バス「大塚二丁目」停留所下車徒歩1分
http://www.ocha.ac.jp/access/index.html
キャンパスマップ:⑤が共通講義棟1号館 ⑥が共通講義棟2号館
http://www.ocha.ac.jp/access/campusmap_l.html
★ご注意:土日は南門が閉まっていますので、正門からお入りください。
会場近くに飲食店がございませんので、昼食はご持参ください。
資料代 1000円(可能な方より、学生無料)
●主催:「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク
後援:文部科学省
内閣府子ども若者・子育て支援施策総合推進室
厚生労働省(申請中)
助成:独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
---------------------------------
9:30 開場
●10:00~12:00 全体会 共通講義棟2号館 101教室
各地の学びサポート・実践報告
・北海道・釧路 NPO法人 地域生活支援ネットワークサロン コミュニティハウス冬
月荘
Zっと!Scrum(みんなで高校行こう会)、まじくるハイスクール(高校就活支
援)
・京都・NPO法人 山科醍醐こどものひろば
楽習サポート のびのび
・東北大学大学院生
地域復興プロジェクト“HARU”の一員として被災地の学習支援に参加して
・滋賀県に広がる大津型学習会と全国ネットワークによる学習会の立ち上げ
・さっぽろ若者サポートステーション/札幌市若者支援総合センター
学び直しサポート事業、中学校卒業者等支援事業
学びサポート調査報告(PTより)
〈12:00~13:00 昼休み〉
●13:00~15:45 分科会 共通講義棟1号館
第1分科会 子どもへの直接支援/学び、ごはん・お泊まり
第2分科会 おとなの課題/保護者への対応・運営・諸機関との連携
第3分科会 学びリスタート(学び直し)
第4分科会 東日本大震災被災地・避難所での学びサポート
第5分科会 学生ボランティア交流
16:00~16:45 おわりの会
■参加には事前申し込みが必要です。
○申し込みは、こちらへ>>
https://pro.form-mailer.jp/fms/208235bf22017
申し込み締め切り10月25日(火)
○取材申し込みの方は、こちらへ>>
https://pro.form-mailer.jp/fms/907a5d5a22605
※HPトップページからもお申し込み頂けます。
https://end-childpoverty.jp/
■定員200名
定員になりしだい、締め切ります。
参加票は特に発行しませんので、当日受付にて、分科会をご確認のうえ、お支払いを
お願いいたします。
■お問い合わせは、下記へ
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494【当日連絡先】
E-mail mail@end-childpoverty.jp
——————————————-
学びサポートプロジェクトチーム:三輪ほう子、高橋亜美、綿貫公平、酒井勇樹
10月10日(月・祝)学びサポート全国実践交流会事前学習会&実行委員会を開催致します
土曜日, 10月 8th, 201110月10日(月・祝)に、
学びサポート全国実践交流会事前学習会・実行委員会を開催いたします。
お誘い合わせのうえ、ぜひ、ご参加ください。
学生さんの参加、大歓迎です。
■日時:10月10日(月・祝))
13:00~15:30 学びサポート全国実践交流会事前学習会&実行委員会
(参加申込みが必要です)
※終了後、引き続きネットワーク会議を開催します。 (15:45~17:00)
ネットワーク会議はどなたでも参加できますので、ふるって
ご参加ください。
★場所:お茶の水女子大学/〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
共通講義棟1号館204教室(前回の隣の教室)
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分
都営バス「大塚二丁目」停留所下車徒歩1分
http://www.ocha.ac.jp/access/index.html
キャンパスマップ:5番が共通講義棟1号館
http://www.ocha.ac.jp/access/campusmap_l.html
ご注意:祝日は南門が閉まっていますので、正門からお入りください。
■内容
<学習会>
・学びサポートと学生ボランティア活動
岸野秀昭/東京・豊島区 小学生学習支援・クローバー
・低所得世帯の子どもたちへの学びサポートと公的支援について
田中聡子/広島県立大学
<実行委員会>
・学びサポート全国交流会の準備(10月29日(土))について
・学びサポート実態調査について
・学生ボランティア交流について
★参加申込みが必要です。
申し込み方法:件名に「学びサポート実行委員会参加申し込み」と明記し、
①お名前、②お立場・ご所属、③お住まいの都道府県、④電話番号をご記入のうえ、
10月9日(日)までに下記宛てお送りください。
メールアドレス mail@end-childpoverty.jp
10月10日(月・祝)には、ご参加になれない方でも、10月29日全国交流会当日、
ボランティアとして、お手伝いいただける方は、上記アドレス宛て、お知らせいただ
けますと幸いです。
■全国交流会の概要
10月29日(土) 於:お茶の水女子大学 共通講義棟1号館、2号館
9:30 開場
10:00~12:00 全体会 共通講義棟2号館101
各地の学びサポート・実践報告
・北海道・釧路 地域生活支援ネットワークサロン コミュニティハウス冬月荘
・京都・NPO法人山科醍醐こどものひろば
・さっぽろ若者サポートステーション「学び直しサポート事業」他
学びサポート調査報告(PTより)
13:00~16:00 分科会 共通講義棟1号館
第1分科会 子どもへの直接支援/学び、ごはん・お泊まり
第2分科会 おとなの課題/保護者への対応・運営・諸機関との連携
第3分科会 学びリスタート(学び直し)
第4分科会 東日本大震災被災地・避難所での学びサポート
第5分科会 学生ボランティア交流
16:00 閉会
★詳細は別報いたします。
学びサポートプロジェクトチーム:三輪ほう子、高橋亜美、綿貫公平、酒井勇樹
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-