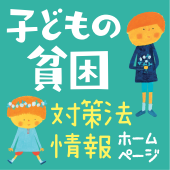3月14日 (木)緊急集会「市民のちからで実効性ある子どもの貧困対策法を」を開催致します
水曜日, 3月 13th, 20133/14(木)に現在法案策定が進められている「子どもの貧困対策法」に関する
緊急市民集会を開催いたします。
当日は、様々なお立場の方々からご発言をいただき、
子どもの貧困対策法を真に実効性のあるものとするために、
みなさまとご一緒に考えあいたいと思います。
市民の願いを届けることが必要です。
新聞、テレビ等、複数の報道機関による取材も入る予定ですので
是非多くの皆様に駆けつけて頂きたいと思います。
また、引き続き「子どもの貧困対策法」に関する要望への賛同(個人・団体)も
募集しておりますので、ぜひともご協力をお願い致します。
●「子どもの貧困対策法」に関する要望 ご賛同のお願い
https://end-childpoverty.jp/archives/1822
以下、緊急集会のご案内となります。
【テーマ】
「市民のちからで実効性ある子どもの貧困対策法を」
【内容】
○団体からの取り組み報告
・あしなが育英会奨学生の立場から
・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
ー被災地支援の現状も踏まえて
・奨学金問題対策全国会議設立の立場から
・生活保護問題対策全国会議から
○「子どもの貧困対策法」制定に関する要望への賛同メッセージのご紹介
○今こそ必要!子どもの貧困対策法ー私たちの声
・大学生から
・しんぐるまざーず・ふぉーらむの方から
・外国にルーツを持つ子どもを支援するお立場の方から
○意見交換
【日時】
2013/3/14(木)19:00~21:00
【場所】
豊島区勤労福祉会館6階 大会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
〒171-0021東京都豊島区西池袋2-37-4
アクセス:池袋駅西口下車 徒歩約10分
池袋駅南口下車 徒歩約7分
◇お車での来館はご遠慮ください。
※2月のネットワーク会議で、
会場を立教大学 池袋キャンパスとお伝えしていましたが、
豊島区勤労福祉会館に変更となりましたのでご注意ください。
【参加費】無料(寄付歓迎)
【参加方法】
この緊急集会はどなたでもご参加になれます。
事前申し込みも不要です。お誘い合わせのうえ、直接会場まで起こしください。
【取材について】
取材をご希望の方は、その旨と取材方法(写真撮影、VTR撮影等)を
下記アドレスまでご連絡ください。
【問い合わせ・当日連絡先】 080-1158-3494
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
2月19日(火)第6回子どもの貧困セミナー 新政権の教育政策の行方を見定める-どの子も排除しない教育をつくる を開催致します
金曜日, 2月 8th, 2013●ご案内チラシはこちらからダウンロードできます↓
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2013/02/2012renzokuseminar_20130219.pdf
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークでは、
2012年度の事業として、子どもの貧困の実態や政策動向を共有し、
子どもの貧困解決に向けてどのような取り組みが求められているかを
皆様と一緒に学びあう連続セミナーを企画しております。
第6回セミナーは、現在、急ピッチで進められようとしている教育政策に
焦点を当てます。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク 世話人会
以下、「転送歓迎」です。――――――――――――――――――――――――
「子どもの貧困」を考える連続セミナー
第6回 :新政権の教育政策の行方を見定める
――どの子も排除しない教育をつくる
【概要】
第二次安倍政権は目玉政策の一つに「教育改革」を掲げ、
学校や教育委員会の仕組みを変えるプランを提示しています。
その内容とねらいを検討し、子どもにどのような影響を及ぼすかを
考えてみましょう。
また、すでに進められている大阪での改革は、他の地域でも起きており、
これからどの地域でも起きる可能性があります。
政権交代にかかわらず、新自由主義的改革について分析することなしには、
今の教育を考えることはできないでしょう。
【報告者】
中嶋哲彦(名古屋大学)
(「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人)
【日時】
2013年2月19日(火)19:00~20:30(18:30開場)
【場所】がんばれ! 子供村 4階研修室
アクセス/JR、東京メトロ、西武池袋線、東武東上線、池袋駅徒歩10分
東京メトロ雑司が谷駅 1番出口/ 都電荒川線鬼子母神前駅 徒歩7分
都電荒川線雑司が谷駅 徒歩10分
地図 http://kodomomura.com/access.html
〒171-0032
東京都豊島区雑司ヶ谷3-12-9
■資料代:500円 (可能な方より)
★事前申し込みが必要です
参加ご希望の方は、件名に【第6回連続セミナー申し込み】と明記のうえ、
①お名前、②お立場・ご所属、③お住まいの都道府県、④電話番号を
ご記入のうえ、2月18日(月)までに、下記のアドレス宛てに
お申し込みください。
※当日参加も可能です。受付にて受付票をご記入ください。
定員:50人(定員になりしだい締め切ります)
資料代:500円(可能な方より 学生無料)
特に参加票は発行いたしませんので、当日、会場にて、
受付・資料代のお支払いをお願いいたします。
★取材ご希望の方は、その旨と取材方法をお申し添えください
※セミナー終了後、20:30から21:00までネットワーク会議を開催します。
こちらもふるってご参加ください。
■問い合わせ・当日連絡先:080-1158-3494
【主催】
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
【助成】
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
「就学援助制度に関する調査」集計結果のご報告(第二次報告)
水曜日, 1月 23rd, 2013「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク調査チームでは
就学援助に関する自治体施策の実態調査を実施し、
昨年10月に第一次報告として発表しました。
今回、第一次報告に掲載していない自由記述回答部分について記載し、
第二次報告としてまとめて、ホームページに掲載しました。
※その際、第一次報告には一部記載の不備がありましたので修正を加えています。
●『就学援助制度に関する調査』集計結果 第二次報告は
以下のURLからダウンロードできます。
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2013/01/201301syuugakuennjo_tyousa_2nd.pdf
みなさまには、自治体の就学援助施策の拡充に向けたとりくみに
今後とも引き続きご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
調査チーム担当:湯澤直美、山野良一、川松亮
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションへの賛同について
火曜日, 1月 22nd, 2013みなさまもすでに報道等でご存知かと思われますが
現在、政府与党は社会保障審議会・生活保護基準部会での審議を踏まえ
生活保護基準の引き下げを決定しようとしています。
その生活保護基準の引き下げの動きに対し、
宇都宮健児、稲葉剛、雨宮処凛、荻原博子、森永卓郎、布川日佐史ほか
13人の方々が呼びかけ人となって「STOP!生活保護基準引き下げ」
アクションを行なっており、広範な団体・個人が結集しています。
http://nationalminimum.xrea.jp/
私たち「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会は
昨年11月に厚生労働大臣宛て、12月に財務大臣・文部科学大臣宛てに
「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」を提出しております。
生活保護世帯のみならず、貧困・低所得世帯の子どもたちの学びと暮らしの悪化に
さらなる追い打ちをかける今回の生活保護基準の引き下げに
反対の意思表明をしております。
そこで私たち「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会として
「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションへの賛同を決定致しましたので
ご連絡させて頂きます。
【賛同メッセージ】
2009年に続き、2011年に厚生労働省により相対的貧困率が公表され、
日本における深刻な「子どもの貧困」の実態が改めて確認されました。
子どもの貧困率の上昇(14.2%→15.7%)とともに暮らしの困難は悪化の一途を
たどっているにもかかわらず、解決のための政策は着手されないままです。
それどころか、このたびの生活保護基準の引き下げの動きは、
就学援助など関連制度にも影響を与え、生活保護世帯のみならず
貧困家庭における子どもたちの学びと暮らしの悪化に、
さらなる追い打ちをかけることにならざるをえません。
私たち「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会は
STOP!生活保護基準引き下げアクションに賛同いたします。
また、現在「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションでは
生活保護基準引き下げに反対する署名活動を行なっており、
http://nationalminimum.xrea.jp/shomei
本日1月22日には、署名提出行動と緊急記者会見を
予定しておりますので、合わせてお知らせ致します。
http://nationalminimum.xrea.jp/event/
なお、お知らせしております通り、
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークでは
1月28日に、現在の生活保護制度について学ぶ
以下のセミナーを企画しております。
みなさまのご参加をお待ちしております。
「子どもの貧困」を考える連続セミナー
第5回:生活保護の「今」を学ぶ -子どもの貧困と生活保護制度
【講師】
池谷秀登さん(帝京平成大学現代ライフ学部教授)
【日時】
2013年1月28日(月)19:00時~20:20時(18:30開場)
※セミナー終了後ネットワーク会議を開催いたします。(20:20~21:00)
【場所】
★ふだんと違う会場です。おまちがいのないよう、お出かけください。
豊島区勤労福祉会館6階 第7会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
〒171-0021東京都豊島区西池袋2-37-4
★事前申込みが必要です。詳しくはHPをご覧下さい。
https://end-childpoverty.jp/archives/1790
以上、ご連絡致します。
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
1月28日(月)第5回子どもの貧困セミナー 生活保護の「今」を学ぶ-子どもの貧困と生活保護制度 を開催致します
火曜日, 1月 15th, 2013●ご案内チラシはこちらからダウンロードできます↓
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2013/01/20122012renzokuseminar_20130128.pdf
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークでは、
2012年度の事業として、子どもの貧困の実態や政策動向を共有し、
子どもの貧困解決に向けてどのような取り組みが求められているかを
皆様と一緒に学びあう連続セミナーを企画してまいりました。
12月の第4回に続き、第5回目のセミナーを次のとおりご案内いたします。
「セミナー」のみの参加、その後の「ネットワーク会議」のみの参加、
どちらも参加、ともにOKです。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク 世話人会
以下、「転送歓迎」です。――――――――――――――――――――――――
「子どもの貧困」を考える連続セミナー
第5回:生活保護の「今」を学ぶ -子どもの貧困と生活保護制度
【講師】
池谷秀登さん(帝京平成大学現代ライフ学部教授)
【日時】
2013年1月28日(月)19:00時~20:20時(18:30開場)
※セミナー終了後ネットワーク会議を開催いたします。(20:20~21:00)
【概要】
私たちにかかわりが深くて、しかし十分よく知らない生活保護制度。
昨年はタレントの親族の受給問題から、生活保護バッシングが広がりました。
生活保護は今どうなっているのか、
日本の社会でどういう役割を果たしているのか、
実務はどう進められていて、
これからどうなろうとしているのか。
特に、新厚生労働大臣が明言している生活保護基準の引き下げは、
私たちの暮らしにどのような影響を及ぼすのでしょうか。
日本の生活保護制度の経緯にも触れながら
現状とこれからどういう方向に行こうとしているのか
お話をお聞きしたいと思います。
私たちの今後の活動の基礎知識として
生活保護について、わからないことを聞いてみませんか?
講師は、福祉事務所で長く生活保護の実務に携わった経験のある研究者です。
【場所】
★ふだんと違う会場です。おまちがいのないよう、お出かけください。
豊島区勤労福祉会館6階 第7会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
〒171-0021東京都豊島区西池袋2-37-4
アクセス:池袋駅西口下車 徒歩約10分
池袋駅南口下車 徒歩約7分
◇お車での来館はご遠慮ください。
【参加申込み】
★事前申し込みが必要です
参加ご希望の方は、件名に【第5回連続セミナー申し込み】と明記のうえ、
①お名前、②お立場・ご所属、③お住まいの都道府県、④電話番号を
ご記入のうえ、1月27日(日)までに、下記のアドレス宛てに
お申し込みください。
※当日参加も可能です。受付にて受付票をご記入ください。
定員:40人(定員になりしだい締め切ります)
資料代:500円(可能な方より: 学生無料)
特に参加票は発行いたしませんので、当日、会場にて、
受付・資料代のお支払いをお願いいたします。
★取材ご希望の方は、その旨と取材方法をお申し添えください
■問い合わせ・当日連絡先:080-1158-3494
【主催】
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
【助成】
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
12月22日(土)第4回子どもの貧困セミナー「子どもの貧困」に挑む若者たちの声 ~知ってほしい、私たちの思い~ を開催致します
月曜日, 12月 17th, 2012●ご案内チラシはこちらからダウンロードできます
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/12/2012renzokuseminar_1222.pdf
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークでは、 2012年度の事業として、
子どもの貧困の実態や政策動向を共有し、 子どもの貧困解決に向けて
どのような取り組みが求められているかを 皆様と一緒に学びあう連続セミナーを
企画しております。
第4回にあたる今回のセミナーは、 子ども支援に関わる若者の相互交流を行う団体
CYCLE(サイクル)との共催で 「子どもの貧困」問題に取り組む若者たちに焦点を当てます。
皆さんもご存知の通り、現在、全国各地で学びサポートや学費問題など
「子どもの貧困」問題に関わる若者が増えてきています。 今回はそのような若者たちに
集まって頂き、普段聞く事のできない 若者たちの活動への思いや問題意識を持つきっかけ、
どう将来にいかしていくか、 またこれらの活動を通してどう将来が変わったか、
社会に訴えたい事など・・・ 若者たちに本音を語ってもらいます。
若者に関わる大人、若者の力を借りたい大人、若者から元気をもらいたい大人には
ぜひご来場いただき、希望に満ち溢れた2012年の締めくくりとして頂ければと思います。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク 世話人会
以下、「転送歓迎」です。――――――――――――――――――――――――
「子どもの貧困」を考える連続セミナー
第4回:「子どもの貧困」に挑む若者たちの声 ~知ってほしい、私たちの思い~
【概要】
各地で学びサポートや学費問題など「子どもの貧困」問題に取り組む若者が、
活動への思いやきっかけなどを語り合い、同じく子どもの貧困問題に取り組む
おとなたちや広く社会に発信します。
【日時】
2012年12月22日(土)16時~19時(15:40開場)
【場所】
荒川区 尾久ふれあい館
http://advance2.pmx.proatlas.net/i2246b29/detail.php?no=260
アクセス:都電荒川線「小台」下車 徒歩3分
〒 116-0011 荒川区西尾久二丁目25番13号
【プログラム】
15:40 受付開始
16:00 開会
第1部 全体会/若者パネルディスカッション
●発言者(所属団体)
荒井佑介(CYCLE)
岩井佑樹(反貧困ネットワーク)
岩崎千慧
岸野秀昭(CYCLE)
権田真都(クローバー)
白谷素子(宿題カフェ)
清野駿平(池袋本町プレーパーク)
土方真知
調布中NGO 高校生2名
ほか予定
(休憩)
17:00 第2部 グループ討論
18:00 第3部 全体会/共有と質疑応答
19:00 閉会
●ご案内チラシはこちらからダウンロードできます
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/12/2012renzokuseminar_1222.pdf
★事前申し込みが必要です
参加ご希望の方は、件名に【第4回連続セミナー申し込み】と明記のうえ、
①お名前、②お立場・ご所属、③お住まいの都道府県、④電話番号を
ご記入のうえ、12月20日(木)までに、下記のアドレス宛てに
お申し込みください。
定員:50人(定員になりしだい締め切ります)
資料代:500円(可能な方より 学生無料)
特に参加票は発行いたしませんので、当日、会場にて、
受付・資料代のお支払いをお願いいたします。
★取材ご希望の方は、その旨と取材方法をお申し添えください
■問い合わせ・当日連絡先:080-1158-3494
【主催】
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク・CYCLE
【協力】
荒川区 尾久ふれあい館(NPO法人ワーカーズコープ運営)
【助成】
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-
12月4日(火)文部科学大臣宛て「生活保護認定基準の引き下げ撤回及び就学援助の改善・充実に関する要望」提出のご報告
水曜日, 12月 5th, 2012各位
2012年12月04日
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
共同代表 平湯真人
湯澤直美
三輪ほう子
子どもたちの学びと暮らしをこれ以上悪化させないために
「生活保護認定基準の引き下げ撤回及び
就学援助の改善・充実に関する要望」提出報告
ご存知の通り、現政権が日本の子どもたちの貧困状況を認めてからも、
子どもの貧困状況は改善されず、悪化の一途をたどっています。
このたびの生活保護基準の引き下げの動きは、それら貧困家庭における
子どもたちの学びと暮らしをさらに悪化させることに他なりません。
子どもたちの貧困問題解決のために、私どもは下記2点を要望としてまとめ、
12月4日、文部科学大臣に提出いたしました。
1 生活保護の受給を困難にする生活保護基準の引き下げを撤回させること
2 就学援助制度については、経済的に困窮する人々が利用しやすいように、必要な措置を
拡充すること
要望の詳細は添付資料をご参照下さい。
添付資料
1 「生活保護認定基準の引き下げ撤回及び就学援助の改善・充実に関する要望」
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/12/20121204seikatsuhogo_youbousyo_monka.pdf
問合せ:「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
12月4日(火)財務大臣宛て「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」提出のご報告
水曜日, 12月 5th, 2012各位
2012年12月04日
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
共同代表 平湯真人
湯澤直美
三輪ほう子
子どもたちの学びと暮らしをこれ以上悪化させないために
「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」提出報告
ご存知の通り、現政権が日本の子どもたちの貧困状況を認めてからも、
子どもの貧困状況は改善されず、悪化の一途をたどっています。
このたびの生活保護基準の引き下げの動きは、それら貧困家庭における
子どもたちの学びと暮らしをさらに悪化させることに他なりません。
子どもたちの貧困問題解決のために、私どもは下記の要望を、
12月4日、財務大臣に提出いたしました。
○ 生活保護の受給を困難にする生活保護基準の引き下げをさせないこと
要望の詳細は添付資料は添付資料をご参照ください。
添付資料
1 「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/12/20121204seikatsuhogo_youbousyo_zaimu.pdf
問合せ:「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
11月26日(月)厚生労働大臣宛て「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」提出のご報告
月曜日, 11月 26th, 2012各位
2012年11月26日
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
共同代表 平湯真人
湯澤直美
三輪ほう子
子どもたちの学びと暮らしをこれ以上悪化させないために
「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」提出報告
ご存知の通り、現政権が日本の子どもたちの貧困状況を認めてからも、
子どもの貧困状況は改善されず、悪化の一途をたどっています。
このたびの生活保護基準の引き下げの動きは、それら貧困家庭における
子どもたちの学びと暮らしをさらに悪化させることに他なりません。
子どもたちの貧困問題解決のために、私どもは下記2点を要望としてまとめ、
11月26日、厚生労働大臣に提出いたしました。
1 生活保護の受給を困難にする生活保護基準の引き下げを撤回すること
2 生活保護制度を経済的に困窮する人々が利用しやすいように改善すること
詳細は添付資料、並びに、10月に発表いたしました
「就学援助制度に関する調査」集計結果報告につきましてもご参照いただければ幸いです。
添付資料
1 「生活保護基準の引き下げ撤回の要望」
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/11/20121126seikatsuhogo_youbousyo.pdf
2 「就学援助制度に関する調査」集計結果報告(第一次報告)
https://end-childpoverty.jp/wp-content/uploads/2012/10/201210syuugakuennjo_tyousa_1st.pdf
問合せ:「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
11月7日(水)第3回子どもの貧困セミナー「大阪幼児置き去り死事件-裁判傍聴を通じて見えてきたこと」を開催致します
月曜日, 10月 29th, 2012~定員に達しましたので、受付は終了しました~
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークでは、
2012年度の事業として、子どもの貧困の実態や政策動向を共有し、
子どもの貧困解決に向けてどのような取り組みが求められているかを
皆様と一緒に学びあう連続セミナーを企画しております。
9月の第2回目に続き、第3回目のセミナーを次のとおりご案内いたします。
「セミナー」のみの参加、その後の「ネットワーク会議」のみ参加、
どちらも参加、ともにOKです。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク 世話人会
以下、「転送歓迎」です。――――――――――――――――――――――――
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク■主催
「子どもの貧困」を考える連続セミナー
第3回:「大阪幼児置き去り死事件」… 裁判傍聴を通じて見えてきたこと
お話:杉山 春さん(ノンフィクションライター)
日時:11月7日(水)18:30~20:20
*終了後「ネットワーク会議」20:30~21:00
場所:立教大学池袋キャンパス 太刀川記念会館 第1・第2会議室
アクセスマップ
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/direction/
キャンパスマップ
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/
<概要>
2010年夏、大阪のマンションの一室から、2人の幼児が衰弱死して
発見されました。母親は風俗産業で働き、夜遊びをして50日間子どもたちを
放置していたとされ、その行状への批判が渦巻きました。
2012年3月、母親である被告に懲役30年の重い刑が言い渡されています。
裁判で分かったことは、被告の生い立ち、そして必死に「いいお母さん」を
めざして子育てしていた事実でした。杉山さんは、裁判の傍聴を続け、
週刊ポスト誌に3回にわたり「ふたつのネグレクト」と題した報告を
書いています。やはり、育児放棄の事件を追った
『ネグレクト/真奈ちゃんはなぜ死んだか』(小学館文庫)で、
小学館ノンフィクション大賞(2004)を受賞しています。
「子どもの貧困」に加えて「子育ての困難」が深刻です。
「子育て」を「個人」のものとせず、地域社会全体の課題として受けとめ、
学び合う機会です。
資料代:500円 (可能な方より)
★事前申し込みが必要です
参加ご希望の方は、件名に【第3回連続セミナー申し込み】と明記のうえ、
①お名前、②お立場・ご所属、③お住まいの都道府県、④電話番号を
ご記入のうえ、11月5日(月)までに、下記の代表メール宛てに
お申し込みください。
~定員に達しましたので、受付は終了しました~
定員:40人(定員になりしだい締め切ります)
特に参加票は発行いたしませんので、当日、会場にて、
受付・資料代のお支払いをお願いいたします。
★取材ご希望の方は、その旨と取材方法をお申し添えください
■問い合わせ・当日連絡先:080-1158-3494
【主催】
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
【助成】
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
——————————————-
「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
TEL 080-1158-3494
E-mail mail@end-childpoverty.jp
HP https://end-childpoverty.jp
——————————————-